きっかけは、あるつぶやきから
「肌育って、結局3型コラーゲンを育てることなんですよね」と、ある美容皮膚科の先生がSNSで呟いていました。
そのとき、ふと気づきました。
「たしかに最近、なんでも“肌育”って言われているな」と。
患者さんだけでなく、医療者のあいだでも
熱や針の治療も、注射製剤も、まとめて“肌育”と呼ばれることが増えているように思います。
でも、よく考えると──そこには異なる作用機序と役割があるように感じています。
肌が美しく見えるために必要なもの
「肌を育てる」と言っても、そのゴールはなんでしょうか?
美容医療では、国際的に「EPCs(Emergent Perceptual Categories)」という視点から、美しい肌の条件を次の4つに整理しています。
- Skin Tone Evenness(色調の均一性)
肌色のムラが少なく、明るく均一に見える - Skin Surface Evenness(表面の平滑)
キメが整い、毛穴や凹凸が目立たないこと - Skin Firmness(ハリ・弾力)
肌が柔軟に弾むような張りがある - Skin Glow(ツヤ・うるおい)
自然なツヤや透明感、そして血色感がある
これら──「うるおい・なめらかさ・ハリ・ツヤ(明るさ)」のバランス。
肌を“育てる”ということは、この4つを土台から整えていくことだと、私は考えています。
コラーゲンには種類がある
「肌のハリをつくるもの」としてよく知られているコラーゲン。
でも実は、一口にコラーゲンといっても、いくつかの種類があるのをご存知でしょうか。
- 1型コラーゲン:もっとも多く存在する、硬くて丈夫な構造材。いわば支柱やロープのような存在です。
- 3型コラーゲン:しなやかさや柔軟性を担う“柔らかい構造材”。若い肌ほど多く含まれています。
- 2型コラーゲン:関節や軟骨に多く、美容皮膚科領域ではあまり出番はありません。
- 4型コラーゲン:基底膜を構成し、表皮と真皮をつなぎとめる“土台”のような存在です。
年齢とともにこれらのコラーゲンは全体的に減っていきますが、
なかでも3型コラーゲンが先に減りやすく、1型優位な構造になっていくといわれています。
すると肌は、ふれて柔らかいのに、どこか“たるんだ”ように見える──
そんな、ちぐはぐな印象が生まれてしまうのです。
創傷治癒という、壊してつくる力
HIFU、高周波(RF)、ニードルRF、ダーマペン、ピコフラクショナル、さらにはジュベルックなどの“炎症誘導型注射”──
これらは共通して、「微細なダメージによって自己修復力を引き出す」治療です。
この過程は創傷治癒と呼ばれ、一時的に3型コラーゲンが産生されますが、最終的には1型コラーゲンを中心とした強靭な構造がつくられます。
つまりこのアプローチは、「肌の支えや厚みをつくる治療」。
美肌の4条件で言えば、ハリ・弾力やなめらかさ・凹凸の改善に関わるものです。
肌育注射が担うのは
一方で、肌に微細な炎症や傷を与えず、
再生の材料や環境を整えることで“育てる”治療もあります。
たとえば──
- PN(ポリヌクレオチド)
- 非架橋ヒアルロン酸(ジャルプロなど)
- アミノ酸(スネコスなど)
これらは細胞を刺激するというよりも、
3型コラーゲンや4型コラーゲンの生成を促し、
肌の柔軟性や自然なツヤ感、うるおいを保つ。
“質感”の改善に欠かせない存在です。
肌の土壌に栄養や水分を与え、柔らかく整えるようなイメージです。
バランスが整って、肌も整う
加齢とともにコラーゲンは減少し、特に3型コラーゲンは先に減ってしまう。
残った1型コラーゲンが支えにはなりますが、肌の柔軟性を失いやすくなります。
だからこそ、
- 支えをつくる「創傷治癒系の治療」
- 質感や柔軟性を補う「肌育注射系の治療」
この2つをバランスよく取り入れることが大切です。
もしエネルギーデバイスばかりに偏ると、肌は引き締まっても、硬さや乾燥、柔軟性のなさが残ることがあります。
逆に、肌育注射だけに頼ると、しなやかさは保たれても、土台の支えが弱い状態になることも。
土台と質感、どちらかが欠けても、理想の肌には近づけません。
育てるという選択
美容医療は今、「治す」でも「守る」でもなく、
“育てる”という視点が大切にされるようになってきました。
肌がなんとなく整っていない
治療を続けているけれど、しっくりこない
そんな方こそ一度立ち止まって、「土台」と「質感」の両方に目を向けてみてほしい。

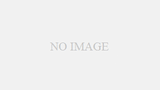
コメント