ハイフという言葉が独り歩き
カウンセリングでは「ハイフってどうなんですか?」というご質問をいただくことがよくあります。 20代の方から、40〜50代の方まで。その関心の広さは、ハイフという治療が多くの方の印象に残っている証かもしれません。
ただ一方で、「ハイフさえやっていれば大丈夫」と感じられているような場面もあり、少しだけ立ち止まって欲しく思ってしまう。 たるみには種類があり、それぞれが起きている”層”も異なるからです。
若い方の”たるみ”とは
高密度焦点式超音波(HIFU)は、SMAS(筋膜)という深い層に熱を届けることで、その層を引き締めて輪郭を整える治療です。
けれど実際には、24歳未満のハイフ適応は日本美容外科学会でも慎重にとされています。 なぜなら、”まだたるんでいない”ことが多いからです。
たとえば20代で「フェイスラインが気になる」という場合、たるみではなく脂肪の厚みによる重さが主な原因というケースもあります。 その場合、脂肪の整理(脂肪溶解や脂肪吸引)や、皮膚の引き締め(高周波やショートスレッドなど)が向いているかもしれません。
ハイフが「効かない」と感じる理由
30代以降では、たるみによる輪郭の変化を感じやすくなります。 けれど、「ハイフを打ってもあまり変わらなかった」という声が出ることも。
この場合、“見ている場所”と“治療の届く場所”がずれていることがあります。 ハイフは顔の外側、フェイスラインの緩みに対してはとても効果的。 ただし、頬の中央や口元、メーラーファットの下垂といった、より内側の構造変化には届きにくいのです。
高周波とショートスレッドの意味
高周波治療(RF)は、真皮や皮下脂肪に熱を加え、線維性組織を再構築するアプローチ。 皮膚が骨の方向へ引き締まることで、口元や頬中央のもたつきにも有効です。
また、ショートスレッドと呼ばれる極細の糸を皮下に挿入する治療は、脂肪層の中のゆるんだ繊維構造を補強し、コラーゲンの再構築を促します。 筋膜ではなく、浅い層を内側から支える治療と言えるかもしれません。皮膚が柔らかいと感じている人には有効かと思います。
皮膚がついてこない
たとえハイフや糸リフトで深い層を整えても、「思ったより上がらなかった」「戻りが早い」と感じることがあります。
それは表層の皮膚や浅層脂肪の支持構造が弱く、引き締まりに追いついていないからかもしれません。 脂肪層はもともと繊維性の隔壁で仕切られていますが、加齢とともにこの構造がゆるみ、脂肪が移動しやすくなるのです。
整えるべきは構造
たるみ治療は、気になる場所だけを見て決めるものではありません。 どの層に、どんな変化が起きているか。 その構造の崩れに合わせて、適切な治療法を選ぶ必要があります。
- 脂肪の重み → 脂肪溶解、脂肪吸引
- 筋膜のゆるみ → ハイフ、糸リフト
- 表層構造のゆるみ → 高周波、ショートスレッド
- 骨の萎縮 → ヒアルロン酸、脂肪注入
- 皮膚構造の質の低下(ハリ・厚み・透明感の低下)→ 肌育注射、エレクトロポレーションなど
こうした組み合わせによって、ようやく「自然に整った輪郭」にたどりつけるのではないかと思っています。
おわりに
ハイフは、筋膜へのピンポイントなアプローチができる、非常に意義深い治療です。 けれど、ハイフ“だけ”で整うことは、実は多くないのかもしれません。
Glowaでは、構造的な視点から「どの層に、どんなアプローチをすべきか」を見極めながら、 必要以上になにかを足さず、けれど確かに整っていく医療をご提案していきたいと考えています。

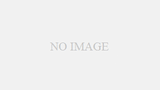
コメント