楽しみにしていた図面
開業準備が少しずつ形になってきた頃、待ちに待った内装レイアウトの打ち合わせがありました。
お願いしたのは、コンサルタントさんを通じてご紹介いただいた設計事務所。
コンペ形式で複数案の提案を募り、いよいよ初回の図面が届く日です。
自分の頭の中にある「理想のクリニック」が、どんなふうに表現されているのか。
その確認と微調整が、今日の目的だと思っていました。
必要最小限、でも機能的に
大きなテナントではない分、スペースを有効に使うことが大前提。
事前にお伝えしていたのは、以下のような構成でした。
- 診察室:2部屋
- オペ室:2部屋
- 処置室:2〜3部屋
- バックヤード
- バックオフィス
- 写真撮影室
- パウダールーム(ブース2つ)
このくらいあれば十分。設計のプロが、その意図を汲み取って整理してくれると信じていました。
図面を見て、言葉に詰まる
ところが当日見せていただいた図面は、どれも「診察室とバックヤードが直結」しており、どこか保険診療クリニックのような雰囲気。
私が美容医療において大切にしたい「安心できる導線」や「個のプライバシー」は、そこにあまり感じられませんでした。
でも、「ここが違うんです」と言葉にして伝えるためには、自分の中にもっと明確なビジョンが必要で…。
うまく話せなかったことが、少し悔しくもありました。
レイアウトもまた、診療の一部
この経験を通して感じたのは、
レイアウトというのは、設計士さんに「任せるもの」ではなく、一緒に「つくっていくもの」なのだということ。
診療スタイルや患者さんの過ごし方、スタッフの動線…。
そうしたイメージが自分の中に育っていなければ、どんな図面を前にしても、判断ができません。
空間設計もまた、“目の前の人の流れ”を思い描くことからはじまる。
診療と、根っこは同じなのかもしれない。そんなことを思った1日でした。
次回予告
初回図面の違和感から、自分でもレイアウトを考えてみることに。
vol.2では、自作ソフトでの試行錯誤と、施術内容から逆算した部屋構成について綴ります。

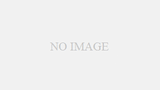
コメント